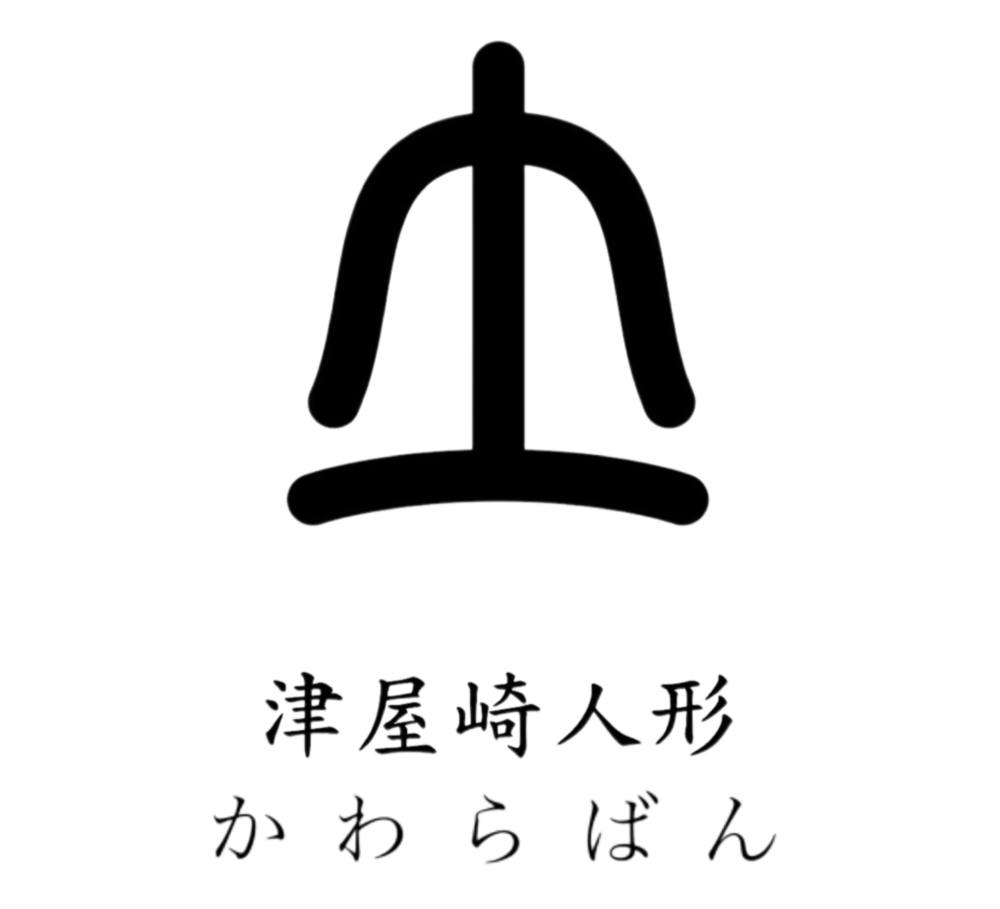私たちの工房がある福岡県福津市津屋崎にはモマ(ふくろう)伝説があります。
これは概略だけが伝わっています。
昔、信仰深い正直者が宮地嶽の山中で道に迷い途方にくれていた時、モマ(ふくろう)に導かれ金の玉を得ました。
「これは神のお授けに違いない」とこの金の玉をお祀したところ、たいそう商売が繁盛したと伝わっています。
概略だけだと、いかにも全国にありそうな縁起話のようで味気ないですね。
今回、勝手に具体的なストーリーを考えてみたので、以下は僕の妄想文(実際の個人や団体とは一切関係ありません)です。
物語としてこんな感じかな?と思いながらモマ笛を作っています。
目次
津屋崎のモマ伝説
津屋崎の海岸沿いの長屋に住む、半兵衛は町でも有名な正直者だった。
近所の人だれもが口を揃え「お前は正直すぎる」と、称賛とも嘲りともとれる言葉をかけた。
近所の小太郎は親切心で「もう少しうまく立ち回れよ」と真顔で注意する。
そのたびに半兵衛は間髪入れず「その方が疲れるだろ」と笑っていた。
人間だれしも発する言葉は階調があり、白黒はっきりさせず、意思を燻した返事をする。
半兵衛にはその心積りがなかった。

役人や坊さんにも疑問があると、自分の信念に従い、「おかしいのでは?」と考えを直接正直に伝える。
まっすぐで、大きな目を開き、淡々と疑問を伝える。
その半兵衛の姿は、信仰深いともいえたが、逆に信仰心の無さと捉える人もいた。
ただ半兵衛は理由なく正直だったわけではない。
正直さもひっくり返すとおおきな理由があった。
半兵衛が幼かったころ、その両親はしょっちゅう家が爆発しそうな喧嘩を起こした。
喧嘩の原因の詳細は今となって思い出すこともできない。
そのころの父親と母親は優しさや思いやりを家庭外に向けており、生じた心の跳ね返りを家庭に持ちかえり解放させていた。
母親はよく「やりきれない」といった。
小声のときも叫び声のときもあったが、同じことを意味していたように思える。これも家庭内のみ聞くことができる言葉だった。
半兵衛が成長すると、商売の対外的なやり取りはすべて半兵衛が担当した。
なんでもきっぱりと正直に話すことが、ありとあらゆる事象に共通する解決策に見えた。
その証拠に、両親は外部とのやり取りがなくなり、不要な仕事が減った。
心労が減った両親は、みるみる穏やかな性格へと変化した。
そんなこんなでやっと仲良くなってきた両親が、今度は仲良く病にかかった。
神様も皮肉なことをするな、半兵衛は思った。
長年の貧乏がたたり、ふたりは痩せすぎであり虚弱であった。
医者曰く、木のみなど栄養価が高いものをお粥に混ぜて食わせという。
栄養価の高い木の実のことを、近所に尋ね回った。
近所の小太郎いわく、宮地の山中には「とちのみ」があり、「あく抜きをすれば栗よりもうまい」とのことだった。
冬を待って、半兵衛1人は宮地山に入った。
とちのみの特徴は、「黄みががった果皮の中に、栗に似た実が入っている」ということだったのだが、割と簡単に見つけることができた。
ナイフで果皮を割ってみると、栗に似た、濃い色をした実が入っている。

しかし思っていたよりも食べられる実は小さく、十分な量を確保するには、麻袋いっぱいになるまで採取が必要である。
半兵衛は必死に実を集め、食べられる部分だけを袋に詰めていった。
ようやく麻袋がいっぱいになり、半兵衛が深くため息をつき、周りを見渡す。
この時ようやく、山のなかで方向を見失っていることに気が付いた。
どちらが山上かもわからない。空も少し薄暗くなっている。
半兵衛は汗の一筋が脇からツーと流れるのを感じた
津屋崎では通年で日が落ちる方が海側だ、半兵衛は海側を目測し駆けだした。
しかし夕日はすでに玄界灘へと沈む寸前だったようだ。
消える前のろうそくのように空がふわっと明るくなったかと思いきや、スッと夜になった。
火を起こすものもなく、持ち物は、ナイフとあくを抜かないと食えない木の実のみ。
防寒も含め大した装備もなしに山に入ったこと、半兵衛はまっすぐに反省した。
暗くなった山は視界に墨をぶちまけたようで、半兵衛は津屋崎の夜の海を思い出した。
海も山も、夜は人間が生活する場所ではないという共通の感覚。
「人間のいるところじゃねえな」、気づいたら半兵衛は周囲に響くようしっかりと言っていた。
返答はなく、白い吐息が言葉の名残として、闇に吸い込まれていく。
半兵衛はいろいろを諦め、麻袋の中の木の実を捨てた。
そこに落ちていた乾いた枯れ葉を敷き詰め、頭に頭巾のように巻きつける。
これで、頭に枝が当たるのを防止する。
しばらくは体力を温存するためその場で待機していたが、山中の独特の寒さから眠くなってくる。
少しでも歩きながら時がすぎるのを待つしかないと腹をくくった。
大きな枝を拾い、杖として、地面を確かめながら、ナメクジのような速度で日が沈んでいった方角と思われる方へとズルズルと進んだ。
性格な時間も方角も分からず、ただ動いていける方へと動いた。
虫でも目標や理由があってうごくだろうに、まるで海中の漂流物のようだなと考えた。
どのくらい歩いただろうか、周りは、静まりかえり、虫や獣の声もしない。ただ、半兵衛の動く音が、「ズリズリ」とするだけであった。

少し山が開け、夜空が見える場所へ出た。
曇ってはいるが、小さな星が2つ見え、活力(というにはほど遠い泡のようなもの)が湧いてきた。
夜空に月は見えないが、森の木々の葉脈の裏側からみると、空はうっすらと明るいのだと気づかされた。
その明るさにほっとするような感覚に浸っていたのに、急に「ホー」という音に、身体が硬直する。
空の少し下、森の闇と空の間にある枝に、人の頭くらいある影があった。
モマ(津屋崎でフクロウを指す)である。
いや正しくは予測される影である。
少し動いているのと鳴き声で、なんとかフクロウと識別できる。
半兵衛は安堵した。
「モマなんてめずらしいな」、半兵衛は自分にしか聞こえない微かな声を出した。
宮地浜で誰かが声を聴いたとかいってたな、と思いながら、すこしずつモマの方へと近づいていく。
ホーという声に近づいても、影は逃げずにそこにあった。
半円型の夜空に飛び出したような枝に、大きな黒い影がひとつ。影のみだが、こちらを見ていることは確実に感じる。
大きな目が二つ、こちらを向いいる。怖さというより、強さを感じて、半兵衛は動けなかった。
見守られているような、見透かされっ手いるような不思議な感覚だ。
すると不意にバサッと乾いた音がして、影が飛び立った。
半兵衛は、光を失ったような焦りを抱いた。
当然暗闇だから、走って追いかけることもできない。
しかし、前方から先ほどよりかなり小さく「ホー」と鳴き声が聞こえるため、少し移動しただけだと安堵した。
きっとこいつには、何か行く先があるに違いない。
ならお供してみるか。時間はたくさんあるし、動かないと凍えそうだ。
いつのまにか鳴き声だけが、この山で目標とできるものとなっていた。
半兵衛は鳴き声を見失わないように、集中しながらも、足元に感覚を研ぎ澄まし、一歩一歩をゆっくりと確実に進んだ。
伸びた草や積み重なった枝葉を、足と右手で持った杖でどかしながら進んでゆく。
枝葉が目に当たったりしたら大変だと、左手で自分の頭の前をかき分けることもやめない。
枝葉や草をかき分ける音、自分の荒い息遣い。
これらは自然の事象ではあるが、今の半兵衛にとって遠くの雑音に過ぎない。
半兵衛は軽く目を閉じた。
無意識に雑音を受け入れたことと、目を保護を目指す二重の意味があった。
迷いはなく、ただ慎重に確実に一歩ずつ。
手に持つ杖が一歩進むごとに微妙にしなっている。
いつかはなにかにたどり着くことを信じて進んだ。
モマの声は、近づいたと思えば遠ざかる。
しかし、確かに声は聞こえるのだった。
もう何時間歩いたかはわからない、振り返るとあっという間だった気もする。
半兵衛の目に薄く光が移る。
海までまっすぐ伸びる道が眼下に伸びていた。
ここからはもう迷わない。
まっすぐ歩くだけで、海岸沿いの家に帰ることができる。
家の玄関に帰りついた半兵衛は、麻袋を頭に巻いたままだと気が付いた。
麻袋をほどいて、土間に置くとコン!という硬い音が響く。
とちのみが残ってたのか、少しでも親に食べさせられるか?頭をよぎった。
袋を広げると、鈍く光る金色の玉が入っていた。
玉を手のひらでもち上げ、朝日を当てて眺めると、やさしい光が移っている。
山中の闇夜に確かに存在したモマの目の光だ。半兵衛はそう感じた。
その後、半兵衛はその玉をしっかりと拝して、両親を懸命に看病した。
看病のかいもあり、両親は完治した。
半兵衛は完治した両親とともに商売に精を出した。
半兵衛は相変わらず正直だったが、たまに断言を避け、相手を思い計らう色があった。
半兵衛の家だけでなく、津屋崎全体の商売は繁盛し、やさしい光がさしこむ場所として末永く栄えたという。